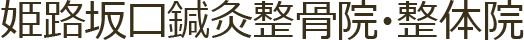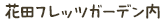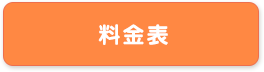2024年07月22日
こんにちは。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院です。
今回は【ぎっくり腰】についてです。
ぎっくり腰とは?
ぎっくり腰は、突然の激しい腰痛を伴う状態のことを指します。
正式には急性腰痛症と言い、重い物を持ち上げた時や急に体をひねった時などに発生することが多いです。
症状 突然の激しい腰の痛み 腰を動かすのが難しくなる 立ったり座ったりするのが辛い 腰が固まって動けなくなることもある
原因 ぎっくり腰の主な原因は以下の通りです:
筋肉や靭帯の損傷:重い物を持ち上げたり、急に体をひねったりすることで筋肉や靭帯が損傷します。
椎間板の問題:椎間板(背骨の間にあるクッションのようなもの)の変性や損傷も原因になります。
姿勢の悪さ:長時間同じ姿勢でいることや、姿勢が悪いことも腰に負担をかけます。
対処法 安静にする:無理に動かず、痛みが落ち着くまで安静にすることが重要です。
冷やす:痛みが強い場合は、初めの48時間程度は冷やすことで炎症を抑えます。
温める:冷やした後は温めることで血行を良くし、回復を助けます。
痛み止め:市販の痛み止めを使うことで、痛みを和らげることができます。
ストレッチ:痛みが和らいできたら、軽いストレッチをすることで筋肉をほぐします。
予防法 正しい姿勢を保つ:長時間同じ姿勢を避け、正しい姿勢を保つことが大切です。
適度な運動:腰や背中の筋肉を鍛えることで、ぎっくり腰を予防します。
重い物を持つときの注意:重い物を持ち上げる際は、腰を曲げずに膝を使って持ち上げるようにします。
ぎっくり腰は突然起こることが多いですが、正しい知識と対処法を知っておくことで、痛みを和らげ、再発を防ぐことができます。
姫路坂口鍼灸整骨院・花田院ではぎっくり腰に対して ハイボルト療法施術を行っています。
まず痛めてから間もない場合、「ハイボルト」という特殊な治療器を用いて施術を行い、 原因となっている筋肉や神経にアプローチします。
この治療器は痛みや炎症に対する即効性が非常に高く、どの筋肉が痛みの原因になっているのかを見つける事が出来ます。
ぎっくり腰の方は1度 姫路坂口鍼灸整骨院花田院へご相談ください。
2024年07月16日
こんにちは。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院です。
今回は【腰の痛み】についてです。
腰の痛みは、多くの人が経験する一般的な問題であり、整骨院での治療が効果的な場合があります。
以下に、整骨院での腰の痛みの治療について分かりやすく説明します。
腰の痛みの原因
腰の痛みの原因は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます。
筋肉の緊張や疲労 椎間板ヘルニア 脊柱管狭窄症 関節炎 姿勢の悪さや生活習慣
整骨院での治療方法
整骨院では、腰の痛みの原因に応じた個別の治療プランを立てます。
主な治療方法は以下の通りです。
手技療法 マッサージ: 筋肉の緊張をほぐし、血行を改善します。
整体: 骨格の歪みを調整し、身体のバランスを整えます。
物理療法 電気療法: 電気刺激を用いて筋肉の緊張を緩和します。
温熱療法: 温かいパッドやホットパックを使用して筋肉をリラックスさせます。
運動療法 ストレッチ: 筋肉の柔軟性を高め、痛みを軽減します。
筋力トレーニング: 腰や腹部の筋肉を強化し、再発を防ぎます。
生活指導 姿勢指導: 正しい姿勢や動作を指導し、日常生活での負担を減らします。
生活習慣の改善: 食事や運動、睡眠など、健康的な生活習慣を推奨します。
整骨院の利用方法
整骨院とは、柔道整復師が骨格や筋肉の問題を手技や物理療法を用いて治療する場所です。
柔道整復師は、国家資格を持つ専門家で、骨折や脱臼、打撲、捻挫などの外傷治療を中心に行いますが、腰痛などの慢性的な痛みの改善にも対応しています。
腰の痛みを感じたら、まずは整骨院に相談しましょう。
初診時には、症状や生活習慣について詳しく聞かれますので、正直に答えることが大切です。その上で、柔道整復師が最適な治療プランを提案してくれます。
整骨院での定期的な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。 腰の痛みは早期に対処することで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
整骨院での専門的な治療を受けて、健康な体を取り戻しましょう。
腰の症状でお困りお悩みの方は1度
姫路坂口鍼灸整骨院花田院へご相談ください。
2024年07月11日
こんにちは。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院です。 😛
どれだけ運転や行動を気をつけていても交通事故のリスクはあります。
何もないのが一番ですが万が一事故に遭われた場合
身体にでる症状に対して治療が必要となります。
今回は事故して整骨院でどのようなことをするのか説明します。
交通事故に遭った場合、体に受けるダメージは予想以上に大きいことがあります。
事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくいこともありますが、数日後に症状が出てくることがあります。
こうした交通事故によるケガや痛みの治療には、整骨院が利用されることが多いです。
整骨院での交通事故治療の特徴
診察と評価: 整骨院ではまず、患者の状態を詳しく診察し、ケガの程度や痛みの原因を特定します。
問診や触診、場合によっては画像診断などを行い、治療方針を決定します。
治療方法:
手技療法(マッサージや整体): 筋肉や関節の状態を整え、痛みを軽減します。
物理療法: 温熱療法や電気治療、超音波治療などを用いて、血行を促進し、炎症を抑える効果があります。
運動療法: リハビリとしてのストレッチやエクササイズを指導し、筋力を回復させ、再発を防ぎます。
保険適用: 交通事故の治療には、自賠責保険が適用されることが多いです。
この保険を利用することで、自己負担を少なくして治療を受けることができます。
交通事故特有の症状に対応: むち打ち症: 交通事故でよく見られる首のケガで、首や肩の痛み、頭痛、めまいなどの症状が現れます。
腰痛や背中の痛み: 衝撃による筋肉や関節の損傷が原因です。
通院の柔軟性: 整骨院は夜遅くまで開いていることが多く、仕事や学校の後でも通院しやすいです。
整骨院を選ぶ際のポイント 口コミや評判: 実際に治療を受けた人の感想を参考にする。
経験と実績: 交通事故治療の実績が豊富な整骨院を選ぶ。
アクセスの良さ: 通いやすい場所にあるかどうか。 保険対応の確認: 自賠責保険や任意保険が適用されるかどうかを確認する。
交通事故に遭った場合、できるだけ早く整骨院での治療を開始することが、後遺症を防ぎ、早期回復につながります。
もし交通事故に遭った際は、痛みや違和感を感じたら 1度姫路坂口鍼灸整骨院花田院へご相談ください。
2024年07月8日
こんにちは。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院です。 😛
今回は【くび・かたのコリ】についてです。
日常生活においてくびやかたのコリで困っている方は多いと思います。 😥
くび・かたのコリについて、簡単に説明しますね。
1. くび・かたのコリとは?
くび・かたのコリは、首や肩の筋肉が緊張し、硬くなったり痛みを感じる状態のことです。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、悪い姿勢、ストレスなどが原因となることが多いです。
2. 原因
姿勢の悪さ: 長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用で前かがみになり、首や肩に負担がかかります。
ストレス: 精神的なストレスは筋肉の緊張を引き起こします。
運動不足: 運動不足により筋力が低下し、筋肉が硬くなりやすくなります。
冷え: 冷房や寒さによって筋肉が冷え、血行が悪くなることでコリが生じます。
3. 症状
首や肩の痛みや違和感 肩が重く感じる 首や肩の動きが制限される 頭痛や目の疲れを伴うこともあります
4. 対策と予防
正しい姿勢を保つ: デスクワーク時には背筋を伸ばし、肘を90度に保つように心がけましょう。
ストレッチ: 定期的に首や肩をストレッチし、筋肉をほぐします。
運動: 筋力を保つために、適度な運動を続けることが重要です。
リラックス: ストレスを溜めないように、リラックスできる時間を持ちましょう。
温める: お風呂や温かいタオルで首や肩を温めると、血行が良くなり、筋肉がほぐれやすくなります。
5. 具体的なストレッチ方法
首の回転: ゆっくりと首を左右に回します。
肩の回転: 肩を前後に大きく回します。
腕の伸ばし: 片方の腕を反対の手で引き、肩や腕を伸ばします。
もし、痛みがひどい場合や改善しない場合は、
姫路坂口鍼灸整骨院花田院に1度ご相談ください。 😀
悩まれている症状に対して治療をさせていただきます。
2024年07月5日
こんにちは。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院です。 😀
坐骨神経痛でお困りではありませんか?
- 腰やお尻の痛み: 主に片側に現れることが多い。
- 太ももやふくらはぎの痛み: 坐骨神経が通る経路に沿った痛み。
- 脚のしびれや感覚異常: ピリピリ感やビリビリ感。
- 筋力低下: 足や脚の筋肉が弱くなること。
- 痛みの増悪: 長時間座ったり、立ち上がったり、くしゃみや咳をしたりすると痛みが悪化する。
- 動作の制限: 動きが制限されることや、痛みを避けるために特定の姿勢をとることが多くなる。
そのままにしておくと…
- 痛みの悪化: 放置することで痛みが強くなり、日常生活に大きな支障をきたすことがある。
- 慢性的な痛み: 急性の痛みが慢性的なものに移行し、長期間にわたる不快感が続く。
- 筋力低下の進行: 足や脚の筋肉がさらに弱くなり、歩行や立ち上がりが困難になることがある。
- 感覚の鈍麻: 脚や足の感覚が鈍くなり、触覚や温度感覚が低下することがある。
- 運動機能の低下: 運動能力が低下し、日常的な動作や運動が難しくなることがある。
- 排尿・排便障害: 重症化すると、膀胱や腸の機能に影響が及び、排尿や排便のコントロールが困難になることがある(馬尾症候群)。
- 精神的なストレス: 持続する痛みや不快感により、精神的なストレスやうつ状態になることがある。
- 姿勢の悪化: 痛みを避けるための不自然な姿勢が続くことで、体全体のバランスが崩れ、他の部位に負担がかかることがある。
痛みをかばうことで姿勢が乱れ骨盤がゆがみます。
それにより身体の一部分に負担が集中してしまい症状の悪化を招いてしまいます。
姫路坂口鍼灸整骨院花田院では姿勢を分析を行い原因となる部分のアプローチ治療を行っております。
さらに身体を支える重要なインナーマッスルを特殊な電気を使って筋力を強化していきます。
坐骨神経痛でお困り方は一度姫路坂口鍼灸整骨院花田院にご相談下さい!
2024年03月9日
こんにちは!
姫路坂口鍼灸整骨院 花田院です☺
産後のこんなお悩みございませんか?
〇肩こりや腰痛がひどい
〇股関節が痛い
〇腕、手首が痛い
〇産後太りが気になる
〇産後の骨盤の歪みが気になる
産後の骨盤が歪んだままだと、お身体に様々な痛みや不調が現れます。
歪んだままだと・・・
まず妊娠するとママの身体はホルモンが分泌され、骨盤周辺の靱帯や筋肉が緩み、骨盤が開きます。赤ちゃんが骨盤を通過し生まれてくると開いていた骨盤は徐々に閉じてきますがすぐには戻りません。
つまり出産後はしばらくは靱帯や筋肉は緩んだままなのですが、そのような骨盤が不安定な状態で家事や育児に動き回ると骨盤が正しい位置に戻らず、歪んだ状態のまま固定されていきます。
身体の土台である骨盤が歪んでいると血流が悪くなりむくみがひどくなったり、老廃物がスムーズに排出されず痩せにくい身体になってしまいます。
また姿勢が崩れることで身体の一か所に負担が集中しやすく、腰痛や肩こり、ぎっくり腰を引き起こしやすくなります。
姫路坂口鍼灸整骨院の産後の骨盤矯正はバキバキ鳴らすようなことは一切行っておりませんのでご安心ください!
ベスト期間は産後2ヶ月~6ヶ月の間で施術を受けて頂くのをオススメします。
※帝王切開の方は3か月からがベストです。個人差はありますので心配な方は一度ご相談下さい。
産後は骨盤だけではなく筋肉も傷んだり硬くなっています。骨盤を元の位置に戻すためには、筋肉も元の状態に戻し骨盤の正しい位置を記憶させることが大切です!